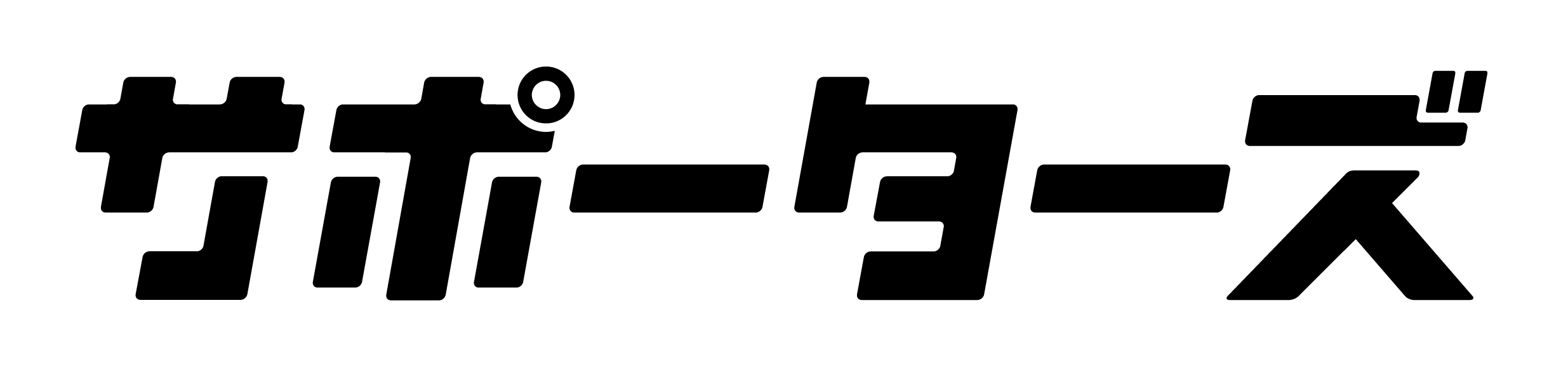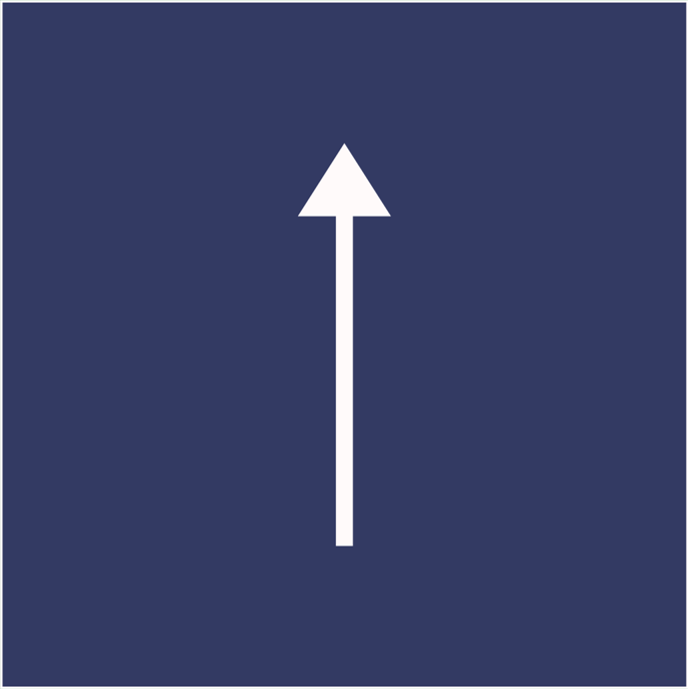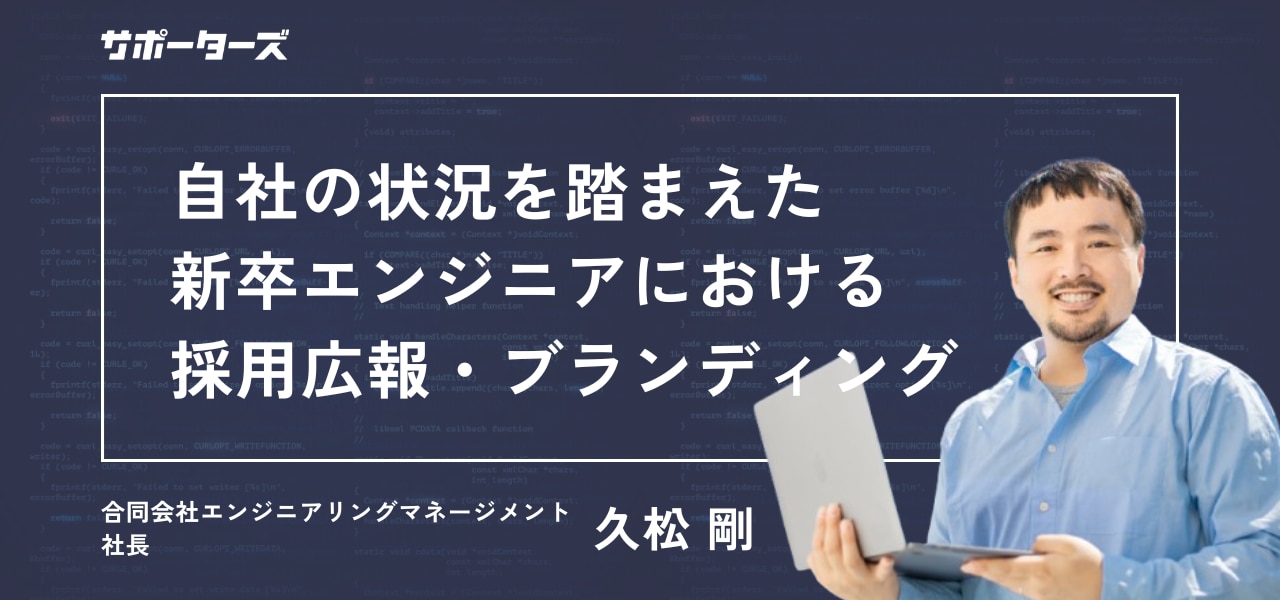
自社の状況を踏まえた、新卒エンジニアにおける採用広報・ブランディング
エンジニア採用において採用広報・ブランディングが占める比重が高まっています。今回は何故比重が高まっているのか、そして新卒においてはどのような観点で展開していくべきかについてお話ししていきます。
目次[非表示]
- 1.重要視される会社の雰囲気
- 2.新卒採用の成功は接触の早さと深さにあり
- 2.1.イベント
- 2.2.社員との交流イベント
- 2.3.インターン
- 2.4.テックブログ
- 3.自社の強みから逆算しよう
重要視される会社の雰囲気
新卒就活生が企業選びをする際に重要視する項目として、「会社の雰囲気」に重きが置かれている傾向にあります。
「会社の雰囲気」を重視する就活生の皆さんにもこれまで多くお会いしてきましたが、特にコロナ禍になってからはリモート採用にシフトしてしまったため、接触する面接官、面談担当者の人柄を「会社の雰囲気」と定義している就活生が多く見られます。
ではウィズコロナ、アフターコロナに突入した現状を想定すると、コロナ禍以前のオフラインを軸にした候補者体験に回帰していくことが想定されます。
※関連資料
新卒採用の成功は接触の早さと深さにあり
内定承諾理由についてのヒアリングを展開していくと、ここ数年の新卒優秀層の採用では下記の2点が鍵となっている傾向があります。
- 早期の接触
- 企業と対象者の時間・コンテンツともに濃厚な接点
次にこれらの要素を鑑み、詳細についてお話をしていきます。
※関連資料
イベント
学生を対象としたイベントには、自社のみによる単独開催のものと、複数企業による共同開催のものがあります。LT大会のようなものから、ハッカソン、アイディアソンといったものまで存在します。
ここ数年、U-30やU-22といった参加者に年齢制限を設けたイベントが見られるようになりました。若手の中では「マサカリ」と「マシュマロ」という言葉が使われることがあります。発表したものに対し、経験者による鋭い切れ味の質問やダメ出しがあることが「マサカリ」とされ、同じような年代の人たちからのフィードバックは「マシュマロ」とされます。
一般的に「マサカリ」には怖い印象が持たれており、ウケは非常に良くありません。イベントを組む上で、自社が出せるスタッフやフィードバック担当者の顔ぶれを意識しながらアプローチを考えていく必要があります。
サポーターズで主催している技育祭なども自社の認知を拡げるという点で有効です。しかしこうしたイベントから直接応募を期待するのはやや気が早いです。
現在自身でも検証しているのですが、登壇の前後でTwitterフォローを促し、そこから中長期的にコンタクトを狙うということをしています。「技育祭でお話をお伺いしていました」というコメントをカジュアル面談で頂くことも多々あり、効果を感じています。
社員との交流イベント
コロナ禍前ではWantedlyなどで公募をする会社さんが見られていました。ジュニア層、未経験者層、若手層に響きやすい傾向があります。
小難しい企業説明会のパートは短めにしつつ、軽食を囲みながらのラフな交流をすることによって社員の人柄が伝わり、満足度が上げられます。採用対象に近しい年齢層で活躍している自社のエンジニアや、エンジニア部門の責任者と交流を持つ場とすることになります。
この際、面接官にも参加して貰うことで、選考でのコミュニケーションが円滑に進む効果があります。コロナ禍で一時期は沈静化しましたが、再燃する可能性があります。
インターン
インターンの早期化が進んでいます。従来であれば春にサマーインターンの母集団形成を行い、夏休み期間中に実施するという流れが一般的でした。
現在ではスプリングインターンなども登場しており、通年でインターン受け入れをしているような状態となっています。
インターンの効能としては、インターン参加者の直接採用だけでなく、インターン参加者からの同期紹介(リファラル)があります。これは10数年前から言われていた手法なのですが、インターンでの良質な経験を学校に持ち帰って貰い、参加者の周囲の優秀な人材を口コミをきっかけに広く集めることで母集団とするというものです。
中にはインターンで表彰されている人材に対して内定が出ず、その周囲の人材に内定が出ているケースもありました。インターンもまた採用広報の一環なのです。
採用広報の観点では、インターン参加者に対してインターンの最後にテックブログを書いて貰うというのも有効です。
やったことや学んだことを軸に記載することで参加者本人が参加企業に対してコミットした感じを強く持てたり、実績としてレジュメに残せるために書類映えするようになるだけでなく、就活中や後輩にあたる読者たちに自社のインターン体験が良好であることを広報することができます。
※関連資料
「エンジニア学生が選ぶ 参加してよかったサマーインターンランキング」から読み解く、人気インターンの特徴
テックブログ
ストア型コンテンツであるテックブログについて、継続的にコンテンツを蓄積しておくことによるブランディング効果や、記事の内容を根拠とした志望動機の高まりが見られます。
技術的な問題に直面した時に「助けられた」「参考になった」という声は新卒・中途の採用シーンではよく耳にします。定期的な技術動向やセキュリティ動向のようなコンテンツであれば、近しい専門領域の学生に「いつも読んでいます」と言って頂くこともあります。
これらのことを踏まえると、テックブログについては継続と、品質の担保が求められます。公開前レビュー時には、技術的な正しさの検証などもしておく必要があります。
自社の強みから逆算しよう
私が採用支援に入る場合、採用に関わる人事やエンジニアを集めて「自社の強み」についてブレストをし、とりまとめるという面接官研修を実施しています。
これは面接時の候補者からの逆質問への回答に繋がるだけでなく、採用広報戦略や会社説明資料への反映でも有効です。もちろん新卒だけでなく中途でも有効です。
また、活躍している若手メンバーへのヒアリングも並行して実施し、とりまとめておくこともお勧めしています。新卒採用したメンバーが望ましいですが、そうでない場合は極力年齢の近い人にインタビューをしましょう。
特に採用ペルソナに近い若手に話を聞くことによって、自社の訴求ポイントや、見え方が明らかになる傾向にあります。
自社の強みが技術力であればテックブログやテックイベントを検討しましょう。強みが会社の雰囲気であれば、それを伝える採用Webサイト、採用動画、就活生との接触イベントなどが想定されます。
まずは自社に備わった良い点を言語化し、訴求ポイントとしていきましょう。
※関連記事
エンジニアから選ばれる採用広報術とは?
▼サポーターズのサービスはこちらからご覧いただけます